- Photo
- Kazumi Kurigami
- Text
- Hirofumi Kurino
- Director
- Sato Takayoshi (OGYA inc)
- Stylist
- Keisuke Baba
- Model
- YACO, Jun Niioka(BARK IN STYLE)
かつて写真は真実を語る道具と位置付けられ、一瞬の美や刹那のエモーションを定着させるもの…とも信じられた。だが本当にそうだろうか?写真は結果であって、その前後は観者が想像する(或いは誤解する)しかない。写真は公平でも解放的でもない。時には対象物を特殊化したり、極端に限定させたりもする。初期の肖像写真が記録した王侯貴族や富裕層の姿は写真という近代装置による‘王権神授説’証明の様にさえ見える。
つまり写真は特権化の道具としても機能してきたのだ。撮られるひとは特別だったと言える。ファッションはある時期までその文脈上にあった。
写真家が職業となり、写真が発表される‘場’が構築され拡大し、芸術の一ジャンルとなる一方で、写真機自体が入手し易くなっていき、ある意味、写真の民主化が進行した。現在に目を移せば、スマートフォンの発達と普及によって‘撮る’ことは当たり前の行為となった。自撮りやインスタグラム、投稿、ソーシャルメディアの普及は写真の在り方を変えつつある。今や誰もが撮る人であり、撮られるひと、でもある。発表の場として長らく特権性を保ってきた雑誌等の存在以上に、いまや全世界のひとが自己メディア化したのだ。
では写真家という職業はどうだろう?前述のロジックだけで言ってしまえば‘誰もが写真家’の時代に従来的な写真家は居場所が無い筈なのだが、
だからこそ、特定の誰かの写真’が際立っている。それはある意味先駆者利益的なものなのかも知れないが…。
ひとがひとを写す。写真家と被写体との関係性は共犯的でもあるだろう。‘写真機=銃‘という論はスーザン・ソンタグによって知られるが、そこにある一方性(写す・Shooting)から生まれる批判や問題意識とは別に、撮る側にも撮られる側にも存在するある種の‘愛’について言及した写真家が操上和美(クリガミ・カズミ)である。
現在89歳の写真家は未だ精力的に驚異的に撮影をこなす。
無理矢理にでもひとことで操上を表せ、と言われたら僕は‘自意識’というキイワードを挙げたい。操上が撮ってきた膨大な作品群の中でもひとは彼の肖像写真に惹かれる。ある対談のなかで操上は‘オレを理解されちゃ困る’ということを言っている。或いは、制約や要求が多い広告の仕事を手掛ける中で‘オレに高額のギャラ払っているんだから、オレの自由にやらせろ‘と言った、とも。一瞬、逆では?ともとれるこの発言は、それでも未だ操上に依頼が途切れない、或いは依頼者自身のハードルを上げてでもしごとを発注してくるその背景と理解できる。
操上和美にしか撮れない結果を期待しているのなら任せて当然だ。
その操上和美と多く仕事をしてきたのが北野武だ。北野も僕にとっては強烈な自意識のひと。そして北野が映画衣装としても個人的にも着てきたのがヨウジヤマモトのふくだ。
一見、静かに見えるが、その底に可視出来ないくらいの濃厚な暗さを湛えたヨウジヤマモトのふくは着手によって、単なるふくを超える。
そして操上和美は2者が起こした結果を一種の魔法に変える。
その魔法は商業施設の中に掲示され、観者つまり来館者によって感知される。来館者は館に並べられたふくに惹き付けられ、客となる。客は単に購入してものを所有した、という取引関係を超えていくかもしれない。
目撃されるべきなにか、はこうして共犯関係のキイとなっていく。
ひとがまちをつくり、まちがひとをつくり、ひとがふくを纏い、写真家はそれを意思を持って画像に写し撮る。写し撮られたものは館で公開され、それをひとが観る。結局、まちには意思を持った館が必要なのだ。
そして僕はこのまちと館に育てられた。
Once, photography was positioned as a tool for speaking the truth, believed to preserve fleeting beauty or momentary emotion. But is that really the case? A photograph is a result, and what comes before or after it is left to the imagination—or misunderstanding—of the viewer. Photography is neither fair nor liberating. At times, it can exaggerate or severely limit its subject. Early portrait photography of royalty and the wealthy looks, in hindsight, like a photographic endorsement of the "divine right of kings."
In other words, photography has also functioned as a tool of privilege. To be photographed was to be special. And for a certain period, fashion operated within this framework.
As photography became a profession, and as platforms for exhibiting photos were established and expanded, the medium entered the realm of art. At the same time, cameras became more accessible, and photography was, in a sense, democratized. In the present day, thanks to the rise and spread of smartphones, taking photos has become a given. Selfies, Instagram, online posts, and social media are transforming the nature of photography. Today, everyone is both a photographer and a subject. The world's people have now become self-publishing media in their own right, surpassing even traditional magazines that long held the privilege of publication.
So what, then, of the professional photographer?
If we follow the logic above, there should be no place for conventional photographers in this age where "everyone is a photographer."
And yet, this is exactly why the work of certain individuals stands out. It may be a kind of first-mover advantage, but...
People photograph people. The relationship between photographer and subject can also be one of complicity. Susan Sontag is known for comparing cameras to guns, but beyond the criticisms and questions of asymmetry implied in "shooting," photographer Kazumi Kurigami has spoken about a kind of "love" that exists on both sides of the lens.
At 89 years old, he still shoots with astonishing energy and vigor.
If I were forced to describe Kurigami in one word, it would be "self-awareness." Among his vast body of work, it is his portraits that continue to captivate. In one interview, he remarked, "It would be a problem if people understood me."
In his advertising work—full of restrictions and demands—he is also known to have said, "You’re paying me a lot, so let me do it my way."
At first, it seems contradictory. But the steady stream of requests, and clients willing to raise their own standards to work with him, speaks to the context behind those words.
If the expectation is for results only Kazumi Kurigami can deliver, then it makes sense to leave it to him.
Takeshi Kitano is one such frequent collaborator. To me, Kitano is also a person with an intense self-awareness. And the clothes Kitano wears—both on screen and personally—are Yohji Yamamoto's.
Yohji Yamamoto's garments may seem quiet at first glance, but beneath the surface lies a rich, deep darkness, invisible to the eye. Through the wearer, the clothing becomes something more.
Kazumi Kurigami turns the result of that union into a kind of magic.
This magic is displayed inside a commercial space and sensed by the viewers—visitors to the site. Drawn by the garments on display, they become customers.
Perhaps this experience transcends the simple transactions of purchase and ownership.
Something which deserves to be witnessed thus becomes the key to a complicit relationship.
People build cities, cities shape people, people wear clothing, and photographers capture this with intention. The captured image is then exhibited in a venue, and people view it.
In the end, a city needs a venue with purpose.
And I have been raised by this city and its venue.
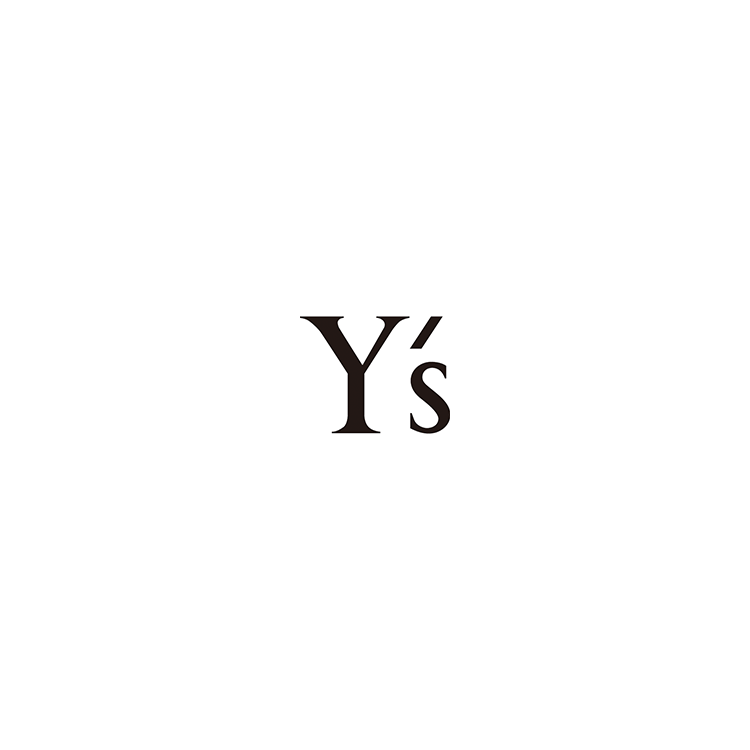
- ブランド名
- Y’s
- フロア
- 3F
- 公式ブランドサイト
- https://www.yohjiyamamoto.co.jp/ys/
- 電話番号
- Y’s Information desk
03-5463-1503(4/24迄)

- ブランド名
- Y’s for men
- フロア
- 3F
- 公式ブランドサイト
- https://www.yohjiyamamoto.co.jp/ys-for-men/
- 電話番号
- Y’s Information desk
03-5463-1503(4/24迄)

- ブランド名
- discord Yohji Yamamoto
- フロア
- 1F
- 公式ブランドサイト
- https://www.yohjiyamamoto.co.jp/discord/
- 電話番号
- 03-6416-5418

- ブランド名
- LIMI feu
- フロア
- 3F
- 公式ブランドサイト
- https://www.yohjiyamamoto.co.jp/limifeu/
- 電話番号
- Y’s Information desk
03-5463-1503(4/24迄)

- ブランド名
- Ground Y
- フロア
- 2F
- 公式ブランドサイト
- https://www.yohjiyamamoto.co.jp/groundy/
- 電話番号
- 03-6427-8984

- ブランド名
- S’YTE
- フロア
- 1F
- 公式ブランドサイト
- https://www.yohjiyamamoto.co.jp/syte/
- 電話番号
- 03-6779-9200

操上 和美(Kazumi Kurigami)
1936年 北海道富良野生まれ。
主な写真集に
『ALTERNATES』『泳ぐ人』『陽と骨』『KAZUMI KURIGAMI PHOTOGRAPHS-CRUSH』
『POSSESSION 首藤康之』『NORTHERN』『Diary 1970-2005』『陽と骨Ⅱ』『PORTRAIT』『SELF PORTRAIT』『DEDICATED』『April』
『50,50 FIFTY GENTLEMEN OF EYEVAN』
主な個展に
「KAZUMI KURIGAMI PHOTOGRAPHS-CRUSH」(原美術館)、
「操上和美 時のポートレイト ノスタルジックな存在になりかけた時間。」(東京都写真美術館)
「PORTRAIT」(Gallery 916)
「Lonesome Day Blues」(キヤノンギャラリーS)
「April」(takaishii gallery)
「Kurigami88」(代官山ヒルサイドテラス・ヒルサイドフォーラム)
2008年 映画『ゼラチンシルバーLOVE』 監督作品。
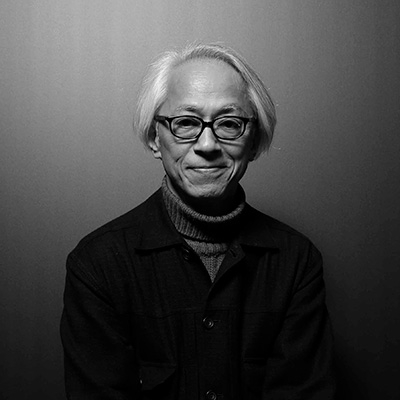
栗野宏文(Hirofumi Kurino)
1953年生まれ。大学では美学を学び、卒業後はファッション小売業に。
スズヤ、ビームスを経て1989年にユナイテッドアローズを創業。2008年まで同社、常務取締役。その間、販売、買付、マネージメント、プレス、ディレクターを経験し、最終的にはCCO(チーフクリエイティヴオフィサー)。
2008年の役員退任後は上級顧問。
2014年よりLVMHプライズの審査員。今年度も継続している。
'モード後の世界'を2020年に上梓。台湾、韓国でも出版されている。

