アートディレクターの千原徹也による初映画監督作『アイスクリームフィーバー』が、7月14日(金)に劇場公開される。
芥川賞作家・川上未映子の短編小説『アイスクリーム熱』を原案に、世代の異なる4人の女性の想いが交錯する姿をつづったラブストーリー。吉岡里帆、モトーラ世理奈、詩羽(水曜日のカンパネラ)、松本まりかが物語の軸となるキャラクターを演じた。
今回は、千原徹也監督、川上未映子、吉岡里帆の3人による鼎談を実施。作品の舞台裏からクリエイティブ論まで、濃密なロングインタビューとなった。
- Photo
- Nico Perez
- Styling
- AYA KUROSAKI(LINX)(Riho Yoshioka)
- Styling
- Saoli Iguchi(Mieko Kawakami)
- Hair&Make
- SayokoYoshizaki(io)(Riho Yoshioka)
- Hair&Make
- Mieko Yoshioka(Mieko Kawakami)
- Text
- SYO
- Edit
- RIDE Inc.


――千原さんにとって、『アイスクリームフィーバー』が初映画監督作になります。公開前のいまのお気持ちはいかがですか?
千原:初めて作ったものに対する怖さを感じています。いままでデザインをやっていてこんな気持ちになったことはないのですが、丸裸の状態で矢面に立っているというか、崖っぷちに立たされている恐怖があります。そんな中でまだ精神を保てているのは、同じくらい楽しみな気持ちがあるから。公開日がすごく楽しみで、毎日ワクワクしている自分もいます。
――本作は元々、千原さんから映画制作の相談を受けた川上さんが『アイスクリーム熱』を薦めたことで具体的に動き出したと伺いました。
川上:千原くんが「映画を撮りたい」と言ったときに、内容以前に「また新しいことをするんだ!」ということに胸を打たれました。私たちは同世代ですが、新しいことをする=その分野の新人になるということですから、素直に凄いなと感じたんです。スターバックスで1時間くらい話したとき、千原くんが「一緒にやりたい」と言ってくれて、これまであまり関心がなかった「自分の小説の映画化」に興味を持てました。そのときにパッと思い浮かんだのが『アイスクリーム熱』です。短編を選んだ理由は、私の中に「原作は短いほどいい」という思い込みがあったから。短い小説を映画にすることで、重層的な内容になるだろうし。
千原:『ジョゼと虎と魚たち』もそうだもんね。
川上:そうそう。そこで千原くんに提案したら「ええやん」って。1時間話したうちの最初の20分くらいで決まりましたね。そこからが長かった。完成、おめでとうございます。
千原:ありがとうございます。『アイスクリーム熱』という原案をどこまで料理していいのか、どこまで自分のやりたいことをやってそこに他の人の考えを取り込んでいくのかを探っていくのに、一番時間がかかったかもしれない。映画は自分にとって神聖なものだから、最初は遠慮もあって探り探りやっていました。
――千原さんは『アイスクリーム熱』をお読みになって、どんな感想を持ちましたか?
千原:川上さんの短編は何本か読んだことがありましたが、ゴールが成功とか失敗じゃないんですよね。この作品も明確なゴールはないんだけど、気持ちがちょっと変わるじゃないですか。誰かが最後に死んだり敵を倒したり、明確な答えを出すための時間じゃなくて、最終的に答えは出なかったとしても気持ちが変わっている――。それを僕は映像表現を通してやりたいと思っていたので、ピタッとハマった感じはありました。


――吉岡さん演じる菜摘とモトーラさん演じる佐保による「女の子同士の話」というアイデアは、川上さんが出されたそうですね。
川上:はい。自分自身、この作品を書き終わったあとに「女の子同士の話だったらもっと長く書けたかも」と思い返すときがあって。この作品を薦めた理由の一つでもありますし、そのアイデアは最初から出ていました。
吉岡:そうだったんですね! 初めて知りました。原作では男女の話だったから、脚本を読んで驚きました。
川上:いまは「シスターフッド」や「エンパワーメント」という言葉が割と使われるようになってきましたが、私の小説には女の人同士の対になっている話が多くて。そういう意味では、自然な流れでした。私はクリエイションにおいて「まだ名付けられていない感情・関係を描けたらいいな」といつも思っています。たとえば私たちが安心できるような恋愛のストーリーに持ち込むんじゃなく、「わからない」という感じをすごく大事にしています。
吉岡:すごく新鮮なお話です。
川上:本当? 嬉しい。
千原:僕自身は「答えを出さないといけない」という固定概念にずっと囚われてきました。手掛けているデザインの仕事は広告が多いので「一個の答えを明確に出して下さい」と求められる。「あの人はどういう気持ちなんですか?」「このシーンにはどういう意味があるんですか?」「なぜ映画を撮りたいんですか?」と聞かれたときに答えを全て持っていないといけなかったのですが、この映画でその感覚が変わったような気がしています。映画の中に「答えがないからこそ私だけのもの」というセリフがありますが、答えを持っていないことを良しとしてくれました。
実際に撮り始めたときも、最初は「“自分の作風”という答え」を出そうとしすぎていたところがあって。「市川崑ならこう撮る、ウェス・アンダーソンならこう」というような感覚に自分自身を当てはめて考えてしまっていたのですが、そう思わなくなってからは吉岡さんたちにも「この映画の空気を感じながら答えを出してもらう」というように、偶発的なものの方が面白いと感じるようになっていきました。
川上:そうなんだ。今回の撮影は、吉岡さんにとっては珍しい経験でしたか?
吉岡:これまでとは全く違いました。今まで参加してきた映画の現場だと、監督と役者とで役に対してのすり合わせを行う時間が結構あるんです。例えば3・4回テストを行ってディスカッションしたうえで本番に進むのですが、今回はそういうかたちじゃなくて“そのまま”を撮る現場でした。ある意味、自分が剥き出しになっている瞬間も撮られているから、ご覧いただいた方に「生々しかった」とよく言われます。今回は初めて芝居をする方もいるので、自然体で撮影できるこの方法はすごく効果的だったと思います。
あと、テイストがわからないことも新鮮でした。私はこの間、三池崇史監督の作品に参加したのですが、例えば三池監督とバイオレンスシーンを撮る際の激しさなど、監督の過去作品を観たうえでイメージして現場に入るんです。でも千原さんは初映画監督だから、参考にできる映画作品がありません。現場でも、初めての演出方法に触れている感覚でした。
千原:撮影初日は、役者が吉岡さんしかいないシーンだったんです。その場に身を置いた吉岡さんの顔が「そういうことね。ここはこういう感じで挑む場なんだ」と悟ってくれて、雰囲気を感じ取って演技してくれたから、ものすごく助けられました。
吉岡:驚いたのが、スタッフさんの多くも初めての映画の現場だったことです。自分が10代のころ初めて学生映画に出たとき、みんな右も左もわからないなか「自分たちはこういうものが好きだ」という気持ちだけで突き進んでいて、あの感じを大人になってもう一度体験できるとは思ってもみませんでした。
千原:映画の現場の経験者が吉岡さんだけだったという(笑)
吉岡:スクリプター(撮影した素材の詳細を記録するスタッフ)もやっていましたから(笑)。雨が降ってきてびちゃびちゃになるシーンがあるのですが、(前のシーンとの)“つながり”のチェックをしながら「大丈夫か!?」みたいに考えたり、詩羽ちゃんが「グリーンの唇も可愛いからやってみたい」と言って、メイクさんも「いいね!」と話しているところに「ちょっと待って!」と割って入って「それをやると今日のシーンだとつながりがおかしくなるから、こっちのシーンの撮影時にやった方がいいかも!」と提案したりして(笑)。そういった経験も面白かったです。そういうなかで、私が「髪型がつながっていないです」と千原さんに伝えたとき「でも画が良かったからOK」と言われて、私の中で「今、私は新しいもの作りの現場にいるんだ」と感じました。
千原:作品づくりで「リアリティ」や「リアリズム」という言葉はよく出てきますが、僕の映画ではちょっとお洒落な恰好をしてくれた方が“ぽい”んですよね。髪型もそうですし、辻褄よりもその部分を意識していくことでこの映画の空気感を生み出せると考えていました。
川上:ちなみに、吉岡さんと千原くんは知り合われてから長いんですか?
吉岡:7年くらい前にお会いして、そこから私のカレンダーのディレクションをずっとお願いしています。
千原:年に1回会う人(笑)。でも今回は、吉岡さん然り「れもんらいふ」や僕のデザインに触れてきてくれた人たちが出てくれたから、言葉にならない刷り込みがあったんじゃないかな。「これは違う」とかリズムみたいなものをわかってくれている気がしました。
――本作には「映画制作を(イチから)デザインする」というコンセプトがあったと伺いましたが、現場のゼロベースの進め方の根底に「千原さんのデザイン」という共通言語があったのですね。
千原:そうだと思います。ただ僕自身では、撮り終えた映像だけでは自分の画の感じや空気、光の答えが見いだせず、編集作業をする中で見つけていきました。デザインって、撮った写真の色味を調整したり文字を入れたり加工する仕事だから、映画制作においてもそうした作業を通して“自分”がわかったといいますか。
吉岡:私も完成した本編を見て、「千原さんは編集の人で、デザインの人だ」と改めて思いました。撮影現場では、あの音や文字の入り方、色と光のバランスは想像しきれていなくて「こんなに可愛い世界になるんだ」「こういう風に時間が交錯していくんだ」と気づかされることが多くありました。例えば菜摘と佐保(モトーラ世理奈)がキスをするかしないかの瞬間のシーンは台本だと一連になっていますが、完成した本編では細切れに使われていて、夢なのか本当なのかわからないフラッシュバックしていく編集の仕方がすごく好きでした。


――川上さんは、完成した作品をご覧になっていかがでしたか?
吉岡:私も気になっています。これは川上さんにお会いしたらお聞きしたかったのですが、物語がここまで『アイスクリーム熱』と変わって大丈夫でしたか?
川上:知らないキャラクターがいっぱい出てきますからね(笑)。じつは、これまで自作が映像化されることに、あまり関心がもてなかったんです。必要を感じなかったというか。でも今回は、すごくいいんじゃないか、と思って。
吉岡:良かった…! 私も川上さんは「映画化しない」というイメージがあったので、初めの印象が「川上さん原案でやれるんですか!?」でした。川上さんの千原さんとの友情関係もあるかと思いますが、「寛大に受け入れてくださった」と千原さん伝いに聞いて本当に嬉しかったです。それと同時に、川上さんが委ねてくださった理由が気になっていて。
川上:自分でもうまく説明できませんが、インディペンデントだったということが大きいのかもしれません。これまでは映画化のお話をいただいても、「これくらいの予算があって、ここにハマる原作を探している」という感じがしてしまうこともあったけれど、今回は全く違うじゃないですか。私はクリエイターがインディペンデントでやるということに敬意を持っているから、「初めてでどうなるかわからない」ということに不安は全くありませんでした。むしろ、未知のところに向かっていこうとする千原くんの創作衝動やチャレンジ精神を信頼できました。
吉岡:私はそこにすごく感動します。ただ仲がいいだけじゃ権利を渡したり「一緒にものづくりをしましょう」とならないと思うんです。でも今回は、プロフェッショナル同士が信頼の元に手を組んでいるのが素敵だなって。
川上:やっぱり、千原くんが資金集めを含めて一人でものすごく頑張ってるのを観てきましたから。映画って世に出るまでが奇跡だと思うんです。もちろん小説も出版されるまですごく長い道のりがありますしみんなができることではありませんが、映画はその比較にならないくらいの人数が関わって、形になるだけでもまず「おめでとう」と言いたい気持ちです。今回は初めてそういう視点で観ることができました。
吉岡:わかります。私も過去に出会った監督さんやプロデューサーさんが予算集めにすごく苦しんでいる姿を目にしてきたので、千原さんの実現力と何年経っても「お願いします」と言ってくださる熱意に心を動かされました。
川上:世に出すことで評価や結果が数字としても出るわけで、それはそれとして受け止めるとして――。基本的に人生一回きりだし、病気になったり大切な人がいなくなったり、明日何が起こるかわからないというのは30歳を過ぎたら絶対にわかっていないといけないことだと思うんです。だからこそクリエイターは、本来は人の顔色を気にしないでやりたいことを好きなようにやるべき。千原くんは40代後半でそれをやってのけて、本当に凄いと思います。
千原:こういう話、始まる前は全然しなかったね(笑)。川上さんは途中段階の脚本や編集中の本編映像を送っても、いつも「ええやん!」と言ってくれていました。
川上:そうそう。「ええやん、ええやん!」ばっかり(笑)。
吉岡:すごくいい話…。答え合わせができた気がして、とても嬉しいです。
川上:私も嬉しいです。クリエイティブって、何でもトライアンドエラーですよね。後から「あのときこうできたかもしれない」と思いながらも、「でもあれ以上のことはできなかった」というその時々の最適解を自分は出したという感触だけが背中を押してくれて、そうやって生きていくしかない。だから、若い人たちがこの映画を観て「自分も何かやってみたい」と思ってくれたら一番嬉しいよね。
千原:そうだね。
川上:色々なものを観てきた人に認められることはとても大事だけど、クリエイションの一番の意義は「自分が何者かわからない」「何をやりたいかもわからない」という人たちに何かを渡すことだと思います。
千原:我々としても、そこに精神を持っていけるかどうかだなと思います。どうしても最初は人の評価を気にしちゃうし、「合ってる?間違ってない?」と考えてしまうものだから。今回は、僕自身が途中から「合ってるも何もない」と思えるようになっていけてよかった。

川上:表現ってどれだけハッピーなものでも、大体人を傷つけてしまうと思っています。受け取る人それぞれに置かれている状況が違うから、例えば私の小説の『黄色い家』というタイトルだけで傷ついてしまう人も必ずいる。だから私たちは、「誰かを傷つけることが避けがたい仕事をしている」という前提を引き受けないといけないと思っています。そのうえで私は、笑顔に代表されるものじゃなくても「とにかくこの時間生きてみよう」というような励まし、エネルギーを手渡したいと考えているし、私自身も求めています。
映画も小説も、私たちがやっている仕事って本当に切羽詰まっている人には無力じゃないですか。その中で私たちがこれに従事しているということを常に考えておかないといけないと、この年になってくるとよく考えます。
『アイスクリームフィーバー』はすごく若くてキラキラしていてフレッシュだから、そうした世界に馴染めない人もいるかもしれません。でも、キラキラしたものがキラキラしたものを表象するわけではなく、暗いものが暗いものを表象するわけじゃない。『アイスクリームフィーバー』という作品とそれを観た人の一過性の出会いで、何かしらのエネルギーが生まれたらいいなと思います。
千原:うちの子どももそうだけど、今の世代の人たちは答えが明確にないと動けない傾向がある気がしています。「A地点に行ってください」と言われると動けるけど、「とりあえず行こうよ」とか「ワクワクを楽しもうよ」ということに意外と慣れていない。映画もゲームも考察を見て答え合わせしたり攻略法を見ながら遊んだりしている印象があります。そういう意味では、エンターテインメント=明確に答えがあるものになりつつある。
でも今回の僕の映画のつくり方って答えがないし、最終的なゴールを「映画館で上映されている」に設定したとしても、その方程式は何だっていい。最終的に美味しい料理ができていれば、調理法は自由なんです。僕のやり方を見て学べという気持ちはさらさらなくて、クリエイティブの向き合い方に対する広い目線を感じてもらえたら嬉しいです。
吉岡:『アイスクリームフィーバー』は、クリエイターとの出会いをくれる作品でもあります。私が演じた菜摘が書くPOP一つとってもイラストレーターさんによるものだったり、テーブルの上に置かれたフィギュアが新進気鋭のアーティストさんのものだったりと、アンテナを張っている人がキュンとするものがたくさん出てきます。
また菜摘は、デザイナーという夢に破れて「自分からデザインを取ったら何も残らない、何もない人間なんだ」と言いますが、そのあと佐保と出会って「まだ自分はやれるような気がする」と思える勇気をもらいます。「必ずしも一人でもがいて夢を掴むものでもない」というストーリーが、私は大好きです。何か頑張っている人と出会ったことで未来が切り開けることもあるので、皆さんぜひ「映画を観る」という名目のもと、少し外に出てみようかなと思ってもらえたら嬉しいです。


――『アイスクリームフィーバー』の舞台の一つが渋谷であり、今日の取材現場も渋谷PARCOです。皆さんの渋谷の思い出を教えて下さい。
千原:僕は京都出身で、年に2回くらい夜行バスで渋谷に来て買い物をしたり、雑誌で見た新しいお店に遊びに行ったりしていました。レコード屋に行ってカフェに行ってセレクトショップに行って洋服を買って、京都には来ていない単館系の映画を観て…。そういうことをやって、また夜行バスで帰っていました。
川上:私にとっては、ほろ苦い街です。元々音楽活動をしていて2000年に大阪から上京したのですが、「街中に色々な音楽が響いているのに、自分の音楽だけが鳴ってない」ということを肌身に感じながら、いつも事務所やスタジオに通っていました。 だからいま、渋谷を歩くと「すごく時間が経ったんだな」と思います。「若い人たちが夢をもってここに来るんだな」と思い出させてくれる街です。
――キャリアを積まれてからも、そのほろ苦さはご自身の中にあるのですね。
川上:ありますし、蘇ってきます。渋谷って「谷」が付いているだけあってアップダウンが激しいですよね。歩くたびにそれを思って、そのことが思い出すスイッチになるところがあります。
吉岡:いまを生きる若者たちが集結して行き交っている感じが、渋谷の魅力でもありますよね。菜摘はその中で埋もれてしまい「どう自分を確立したらいいのか」と悩みますが、どんな人がこの街にいるかわからないくらい人がいるという雰囲気は、渋谷で撮ったからこそ説得力が出たと思います。


――吉岡さんご自身は、渋谷に対する思い出はありますか?
吉岡:映画館が遅い時間まで上映されているので、仕事終わりによく行きます。好きなお店も多いです。でも、あんまり撮影では使わないので今回はレアな経験ができました。まさか渋谷でスケボーする日が来るとは!って(笑)。
今回の撮影で印象に残っているのが、最終的にカットされちゃったのですがスケボーが坂を下りていってしまうというシーン。それをどう撮影するかをスタッフさんが試行錯誤している間、私とモトーラ世理奈ちゃんは休憩していていいよと言われたので、ふたりで現場を抜け出してかき氷屋さんでデートしたんです。あれはすごく楽しかったです。シーン自体は使われなかったけど、その後の菜摘のキラキラした笑顔にはあの時間が活きているように思います。


- 上演作品
- 映画『アイスクリームフィーバー』
- 公開⽇
- 7月14日(金)
- 営業時間
- 11:00〜21:00まで
- 会場
- CINE QUINTO(渋谷ロフト横)/WHITE CINE QUINTO
- 配給
- パルコ
- 公式サイト
- https://icecreamfever-movie.com/
- @icecreamfever_m
© 2023「アイスクリームフィーバー」製作委員会
映画「アイスクリームフィーバー」上映チケット プレゼント
2023年7月7⽇(金)~7月16日(日)の期間中、渋谷PARCO公式SNSにてプレゼントキャンペーンを開催いたします。
下記方法にてプレゼントへご応募ください。
①Instagram(@parco_shibuya_official)公式アカウントをフォロー
②7月7⽇(金)にUPされた公式Instagramの映画「アイスクリームフィーバー」上映チケット プレゼント対象投稿に、「いいね!」とコメントをお願いします。
ご参加いただいた皆さまの中から、抽選で計3組6名様にプレゼントいたします。
ご当選の方へDMにてご連絡致しますので、渋谷PARCO 公式Instagramのフォローをお願いいたします。
※応募はお一人様一回限りと致します。
※既にフォローいただいている方も参加対象となります。
※当選の権利はご当選者様本人のものとし、第三者への譲渡(有償・無償を問わない)・換金を禁止させていただきます。
<当選発表>
厳正なる選考の上、2023年7月下旬頃、当選者にのみインスタグラムのダイレクトメッセージにてご連絡し、賞品の発送をもって当選に代えさせていただきます。また、賞品の発送は2023年7月下旬を予定しております。諸事情により多少前後する場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※期日内にダイレクトメッセージへの応答のない方・当選連絡後、住所等の情報のご提供のない場合は、当選が無効となります。
※当選された方から提供いただきます個人情報は、本キャンペーンの当選のご案内・賞品発送にのみ使用いたします。
※当選理由についてのお問合せは一切受け付けておりません。
※ソーシャルメディアの運用を妨害する行為、趣旨に反する行為、弊社が不適切を判断する行為は禁止致します。
※当キャンペーンはFacebook社Instagramとは一切関係ありません。
※本キャンペーンは、予告なく変更・中止する場合がございますので予めご了承ください。

千原徹也
1975年京都府生まれ。アートディレクターとして、広告(H&Mや、日清カップヌードル×ラフォーレ原宿他)企業ブランディング(ウンナナクール他)、CDジャケット(桑田佳祐 「がらくた」や、吉澤嘉代子他)ドラマ制作、CM制作など、さまざまなジャンルのデザインを手掛ける。またプロデューサーとして「勝手にサザンDAY」主催、東京応援ロゴ「KISS,TOKYO」発起人、富士吉田市の活性化コミュニティ「喫茶檸檬」運営など、活動は多岐に渡る。
Instagram(@thechihara)

Photo:当山礼子
川上未映子
大阪府生まれ。2008年『乳と卵』で芥川龍之介賞、09年、詩集『先端で、さすわ さされるわ そらええわ』で中原中也賞、10年『ヘヴン』で芸術選奨文部科学大臣新人賞および紫式部文学賞、13年、詩集『水瓶』で高見順賞、同年『愛の夢とか』で谷崎潤一郎賞、16年『あこがれ』で渡辺淳一文学賞、19年『夏物語』で毎日出版文化賞を受賞。他の著書に『春のこわいもの』など。『夏物語』は40カ国以上で刊行がすすみ、『ヘヴン』の英訳は22年ブッカー国際賞の最終候補に選出された。23年2月、『すべて真夜中の恋人たち』が「全米批評家協会賞」最終候補にノミネート。最新刊は『黄色い家』。
Instagram(@kawakami_mieko)
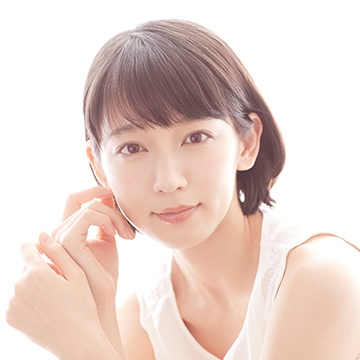
吉岡里帆
1993年1月15日生まれ。京都府出身。連続テレビ小説「あさが来た」(2015)に出演し注目を集める。主な近作にドラマ「レンアイ漫画家」(2021)、「華麗なる一族」(2021)、「しずかちゃんとパパ」(2022)、「ガンニバル」(2022)映画『見えない目撃者』(2019年)、映画『泣く子はいねぇが』(2020)、『ホリック xxxHOLiC』(2022)、『島守の塔』(2022)など。主演映画『ハケンアニメ!』で第46回日本アカデミー賞優秀主演女優賞を受賞。待機作に8月公開の映画『Gメン』、10月公開の『ゆとりですがなにか インターナショナル』、12月公開の映画『怪物の木こり』、9月からWOWOWで放送・配信される「連続ドラマW 落日」など。
Instagram(@riho_yoshioka)




